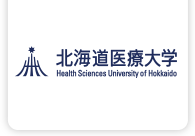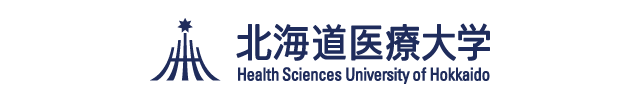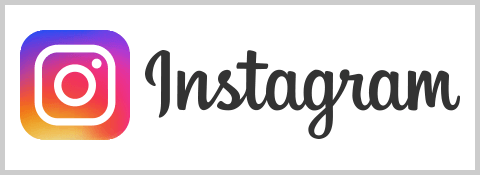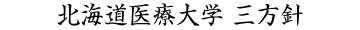- HOME
- 大学概要
- 北海道医療大学 三方針
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
北海道医療大学は、大学および各学部学科の教育理念・教育目的に基づいた教育目標の達成に向けて、全学教育および専門教育科目を履修し、保健・医療・福祉の高度化・専門化に対応しうる高い技術と知識、優れた判断力と教養を身につけ、各学部学科が定める履修上の要件を満たした学生に対して「学士」の学位を授与します。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
北海道医療大学は、教育理念にある「保健と医療と福祉の連携・統合」を基本として、確かな知識と技術、深い教養と豊かな人間性を持ち、広く社会に貢献できる専門職業人の養成に向けた教育課程を編成します。すなわち、幅広く深い教養と豊かな人間性・自立性・創造性・協調性の修得をめざす「全学教育科目」、および確かな専門知識と技術の修得をめざす各学部・学科の「専門教育科目」を適切に組合せた学士課程教育を提供します。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
北海道医療大学は、「21世紀の新しい健康科学の構築」を追究し、社会の要請と期待に応えるため、豊かな人間性や協調性・創造性等に加えて、保健と医療と福祉に関して各学部学科の高度な研究に裏打ちされた専門性の高い教育を行います。本学卒業には各学部学科の「学位授与の方針」の要件を満たすこと、すなわち、全学共通基盤の知識・技術・態度が必要となるばかりではなく高度な専門性の修得が要求されます。そのため、各学部学科では学位授与の方針の要件をより効果的に達成しうる資質を持った人材の受入れについて「入学者受入れの方針」として定めています。
なお、上記の北海道医療大学の三方針(学位授与、教育課程編成・実施、入学者受入れの方針)に基づいて各学部学科の三方針の詳細が定められています。
| 薬学部 | 歯学部 | 看護福祉学部 | 心理科学部 | リハビリテーション科学部 | 医療技術学部 |
薬学部薬学科
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
薬学部薬学科の教育目標に基づき、卒業のために以下の要件を満たすことが求められる。これらの要件には、薬剤師として社会で活躍するための基本的な10の資質*の養成が含まれる。
- 医療人として求められる高い倫理観を持ち、法令を理解し、他者を思いやる豊かな人間性を有する。
- 有効で安全な薬物療法の実践、ならびに人々の健康な生活に寄与するために必要な、基礎から応用までの薬学的知識を修得している。
- 多職種が連携する医療チームに積極的に参画し、地域的および国際的視野を持つ薬剤師としてふさわしい情報収集・評価・提供能力を有する。
- 卒業研究や実務実習を通じて、医療の進歩に対応できる柔軟性と、臨床における問題点を発見・解決する能力を有する。
- 後進の育成に努め、かつ生涯にわたって常に学び続ける姿勢と意欲を有する。
*薬剤師として求められる基本的な資質
① 薬剤師としての心構え ② 患者・生活者本位の視点 ③ コミュニケーション能力
④ チーム医療への参画 ⑤ 基礎的な科学力 ⑥ 薬物療法における実践的能力
⑦ 地域の保健・医療における実践的能力 ⑧ 研究能力 ⑨ 自己研鑽 ⑩ 教育能力
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
薬学部薬学科の学位授与の方針に基づき、全学年を通して、薬学教育モデルコアカリキュラムに基づく教育・研究に加えて本学独自の教育課程を展開する。また、チーム医療の重要性を体験する教育プログラムなどを通して、本学で学んだアイデンティティが自覚できるプログラムを構築する。その教育課程の編成・実施の方針を以下に示す。
- 高い倫理観と豊かな人間性をもつ薬剤師を養成するため、倫理や法規制度に関連する科目ならびにグループ討議を多用したコミュニケーション教育科目を配当する。
- 薬学専門教育へ向けての基礎学力向上を目的とした教育プログラムを低学年において配当する。また、基礎薬学領域から社会薬学領域、衛生薬学領域、医療薬学領域へと順次段階を経て総合的に修得できるよう、専門教育科目を中心とした教育プログラムを展開する。
- 医療系総合大学の利点を活かし、薬剤師を含めた医療従事者の職能を理解し、チーム医療の基礎となる全学部共同の教育科目を配当する。また、長期実務実習を配当し、4年次までに修得した知識・技能・態度を医療現場で実践して、地域的視点および国際的視野を持つ薬剤師として必要な基礎的・応用的能力を養成する。
- 4年次から6年次にかけて、科学者としての薬剤師の能力を涵養するために、配属講座にて少人数制による総合薬学研究を行う。併せて、下級学年の学生の実験指導を通じて、後進の育成の重要性を体感する。
- 科目の評価は、知識領域については主に試験、技能や態度についてはレポート・チェックリスト・ルーブリック等を用いて評価する。薬学実務実習についてはルーブリックをもとに形成的評価を継続的に行い、指導薬剤師および実務家教員による総合評価を行う。卒業研究は、配属講座教員による形成的評価、卒業研究論文および発表会の内容についてルーブリック等を用いて評価する。
- 6年間の統合された学修評価は、1年次から担任との面談(年2回)によって作成されている学生カルテや自己評価シートを用いて、配属講座担当教員との面談によって到達度を評価する。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
薬学部薬学科では、学位授与の方針の要件を修得し、チーム医療を始め地域社会や国際社会に貢献できる自立した薬剤師を養成することを目標としています。そのため、本学科では学位授与の方針の要件を、より効果的に達成しうる資質を持った以下のような人材を広く求めます。
- 保健・医療・福祉活動を通じて社会に貢献しようとする意欲がある人
- 生命を尊重し、他者を理解し、大切に思う心がある人
- 薬学を学ぶ基礎学力*を有し、高い学習意欲のある人
- 主体性を持って様々な人々と協同して学ぶ意欲のある人
- 他の医療スタッフと協働し、薬剤師として活躍したいという強い意志を持っている人
- 薬学分野の様々なことに強い好奇心と探求心を持ち、最新の知識・技術を常に学び続けようとする人
*基礎学力について
薬学部薬学科では、入学後、専門科目の基礎として、医薬品の定量的な扱いのための化学計算、物性の理解のための物理化学、医薬品が作用する生体の働きを理解するための有機化学・生化学などの科目があります。また、世界共通の効果作用を持つ医薬品の理解には英語、そして実験実習には英語論文の理解が必要です。すなわち、高校で学習した数学、英語、化学、生物、物理などの知識や考え方を有効に活用することが学修成果を高めることにつながります。
ここに示す「基礎学力を有し」とは、上記科目を高校で履修していることをさします。
ただし、理科3科目全ての履修は限定されるため、少なくとも1科目を履修しており、未履修の科目については合格後に本学が提供する教育プログラムを受講することを推奨します。
歯学部歯学科
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
歯学部歯学科の教育目標に基づき、卒業のために以下の要件を満たすことが求められる。
- 人々のライフステージに応じた疾患の予防、診断および治療を実践するために基本的な医学、歯科医学、福祉の知識および歯科保健と歯科医療の技術を修得している(専門的実践能力)。
- 「患者中心の医療」を提供するために必要な高い倫理観、他者を思いやる豊かな人間性および優れたコミュニケーション能力を身につけている(プロフェッショナリズムとコミュニケーション能力)。
- 疾患の予防、診断および治療の新たなニーズに対応できるよう生涯にわたって自己研鑽し、継続して自己の専門領域を発展させる能力を身につけている(自己研鑽力)。
- 多職種(保健・医療・福祉)と連携・協力しながら歯科医師の専門性を発揮し、患者中心の安全な医療を実践できる(多職種が連携するチーム医療)。
- 歯科医療の専門家として、地域的および国際的な視野で活躍できる能力を身につけている(社会的貢献)。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
歯学部歯学科の学位授与方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- 歯科医師として必要な基本的知識・技能・態度の修得をめざし、専門基礎科目および専門臨床科目の講義・実習を1年次~4年次に段階的に配当する。また、4年次における共用試験(CBT・OSCE)で基礎項目の評価後、5年次~6年次前期に大学病院、および地域での診療参加型臨床実習を行い、専門的実践能力を養成する。6年次後期には、知識・技能・態度を体系的・総合的に整理し、基本的資質・能力の養成を図る(専門的実践能力)。
- 患者中心の医療を提供し法と倫理を遵守する人間性豊かな歯科医師の養成のために、医療倫理教育および医療コミュニケーション教育を1年次~4年次に段階的に編成する。これらの能力については、4年次における共用試験で模擬的・客観的に評価した後、5年次~6年次前期に配当する診療参加型臨床実習によりさらなる養成を図る。また、6年次後期にそれらを体系的・総合的に整理し、本学科が定めた歯科医師として求められる基本的資質・能力の養成を図る(プロフェッショナリズムとコミュニケーション能力)。
- 研究マインドを涵養し、生涯にわたって自己研鑚を続ける意欲と態度を有する人材の養成を図るため、歯科医学研究科目を編成し、実施する(自己研鑽力)。
- 多職種連携に関する講義・演習を1年次~4年次に段階的に配当し、5年次~6年次前期での診療参加型臨床実習において実践する。さらに6年次後期に多職種連携によるチーム医療を体系的・総合的に整理することにより、基本的資質・能力の養成を図る(多職種が連携するチーム医療)。
- 地域の保健や医療に貢献できる知識と実践的能力養成に向けて演習および診療参加型臨床実習を編成する。また、歯学英語科目に加えて、海外医療時事に関する講義・演習科目および海外臨床研修・実習を実践し、国際的視野の涵養を図る(社会的貢献)。
- 履修科目の学修達成度は、知識に関しては筆記試験やCBT、技能や態度に関してはOSCE、レポート、ポートフォリオ、チェックリストおよびルーブリック等を用いて評価する。診療参加型臨床実習については、ポートフォリオによる継続的な形成的評価およびコンピテンシー試験で基本的な臨床能力を評価する。グローバルマインド、研究マインドの達成度評価には海外臨床研修の研修報告書や各種学術大会等での発表内容、ルーブリック等を用いた活動状況や達成度から検証する。また、歯科医師として具有すべき知識に関して、その達成度を卒業試験で評価し、臨床実習終了時に技能・態度の総括的な評価を行う。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
歯学部歯学科では、学位授与の方針の要件を修得し、多職種連携によるチーム医療をはじめ地域社会や国際社会に貢献できる自立した歯科医師を養成することを目標としています。そのため、本学科では、以下のような資質を持った人材を広く求めます。
- 歯科医師として医療現場で活躍するという強い意志を持っている人
- 生命を尊重し、他者を大切に思う心がある人
- 生涯にわたって学修を継続し、自己を磨く意欲を持っている人
- 保健・医療・福祉に関心があり、地域社会および国際社会に貢献するという目的意識を持っている人
- 入学後の修学に必要な基礎学力*を有している人
*基礎学力について
歯学部歯学科では、専門科目でヒトの体の構造と機能を学ぶとともに歯科治療に用いる様々な材料の物性、化学薬品の性質、検査・治療器具の理論を学びます。そこで生物、物理、化学、数学などの科目を理解し、応用できることが入学後の学修成果を高めることになります。さらに、専門科目を学ぶ際には英語刊行物の理解が必要になることがあり、また、国際化していく医療現場で貢献する準備として英語力が必要になります。ここに示す「基礎学力を有し」とはこれらの科目を高校で履修していることをさします。ただし、理科3科目全ての履修は限定されるため、少なくとも1科目を履修しており、未履修の科目については合格後に本学が提供する教育プログラムを受講することを推奨します。
看護福祉学部看護学科
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
看護福祉学部看護学科の教育目標に基づき、卒業のために以下の要件を満たすことが求められる。
- 人間の生命および個人の尊重を基本とする高い倫理観と豊かな人間性を身につけている。
- 看護専門職に必要な知識・技術を修得し、健康や生活に関する問題に対して、適切かつ柔軟に判断し解決できる学術的・実践的能力を身につけている。
- 社会環境の変化や保健・医療・福祉の新たなニーズに対応できるよう自己研鑽し、自らの専門領域において自律的・創造的に実践する能力を身につけている。
- 保健・医療・福祉をはじめ、人間に関する様々な領域の人々と連携・協働できる能力を身につけている。
- 多様な文化や価値観を尊重して地域社会に貢献できる能力を身につけている。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
看護福祉学部看護学科の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- 看護学科の教育理念を積極的に展開するために、ヒューマンケアの要素である4領域「人間」、「環境」、「健康」、「実践」を設定し、それらの概念を基本として、各領域における授業科目間の順次性と体系性を保つように科目を配当する。
- 1年次では、学修動機の明確化を図り、豊かな人間性や協調性、国際的視野を身につけるための全学教育科目、看護専門職に必要な基礎的知識および看護と福祉に共通するケアマインドを修得するための科目を配当する。
- 2年次では、看護専門職に必要な専門基礎知識・技術、および様々な人々を対象とした看護学の知識と援助方法を修得するための科目を配当する。
- 3年次では、2年次までの学修成果の上に立ち、看護専門職に必要な知識と技術を深めるための講義、演習および実習科目を配当する。また、ヒューマンサービスにおける多職種連携にむけた協調性を身につけるための科目を配当する。
- 4年次では、3年次までの学修成果の上に立ち、理論と実践に習熟し、自らの専門領域を発展させる能力を養成するための実習、専門演習、卒業研究を配当する。
- 主体的な学修を促すために、講義・演習の事前事後の学修課題を提示するとともに、グループワークや発表を取り入れる。
- 学修成果を把握・評価するために、筆記試験、ルーブリックを用いたレポート、実技試験などを実施する。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
看護福祉学部看護学科では、学位授与の方針の要件を修得し、総合的ヒューマンケアを実践し地域社会や人々の健康の向上に貢献できる看護専門職の養成を目標としています。そのため、以下のような資質を持った人材を広く求めます。
- 保健・医療・福祉に関心があり、看護を通じて社会に貢献しようとする意欲がある人
- 生命を尊重し、他者を理解し、大切に思う心がある人
- 看護学を学ぶための基礎学力*を有し、高い学修意欲および探求心のある人
- 看護専門職として保健・医療・福祉の現場で活躍したいという強い意志を持つ人
- 看護専門職として最新の知識・技術を常に学び続けようとする人
*基礎学力について
英語、数学、国語を高等学校等で履修しており、生体の成り立ちや活動を理解するうえで必要となる化学、生物、物理、大学のリベラルアーツ教育の基本となる世界史、日本史、地理、現代社会、政治・経済について、少なくとも1科目以上を履修していることをさします。
看護福祉学部臨床福祉学科
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
看護福祉学部臨床福祉学科の教育目標に基づき、卒業のために以下の要件を満たすことが求められる。
- 人間の生命および個人の尊重を基本とする高い倫理観と豊かな人間性を身につけている。
- 福祉専門職に必要な知識・技術を修得し、健康や生活に関する問題に対して、適切かつ柔軟に判断し解決できる学術的・実践的能力を身につけている。
- 社会環境の変化や保健・医療・福祉の新たなニーズに対応できるよう自己研鑽し、自らの専門領域において自律的・創造的に実践する能力を身につけている。
- 保健・医療・福祉をはじめ、人間に関する様々な領域の人々と連携・協働できる能力を身につけている。
- 多様な文化や価値観を尊重して地域社会に貢献できる能力を身につけている。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
看護福祉学部臨床福祉学科の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- 臨床福祉学科の教育理念を積極的に展開するために、ヒューマンケアの要素である4領域「人間」、「環境」、「健康」、「実践」を設定し、それらの概念を基本として、各領域における授業科目間の順次性と体系性を保つように科目を配当する。
- 1年次では、学修動機の明確化を図り、豊かな人間性や協調性、国際的視野を身につけるための全学教育科目、福祉専門職に必要な基礎的知識および看護と福祉に共通するケアマインドを修得するための科目を配当する。
- 2年次では、福祉専門職に必要な専門基礎知識および様々な人々を対象とした知識と援助方法を修得するための専門教育科目を配当する。
- 3年次では、2年次までの学修成果の上に立ち、福祉専門職に必要な知識と技術を深めるための講義、演習および実習科目を配当する。また、ヒューマンサービスにおける多職種連携にむけた協調性を身につけるための科目を配当する。
- 4年次では、3年次までの学修成果の上に立ち、理論と実践に習熟し、自らの専門領域を発展させる能力を養成するための実習、専門演習、卒業研究を配当する。
- 主体的な学修を促すために、講義・演習の事前事後の学修課題を提示するとともに、グループワークや発表を取り入れる。
- 学修成果を把握・評価するために、筆記試験、ルーブリックを用いたレポート、実技試験などを実施する。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
看護福祉学部臨床福祉学科では、学位授与の方針の要件を修得し、総合的ヒューマンケアを実践し地域や人々の健康の向上に貢献できる福祉専門職の養成を目標としています。そのため、以下のような資質を持った人材を広く求めます。
- 保健・医療・福祉に関心があり、福祉を通じて社会に貢献しようとする意欲がある人
- 生命を尊重し、他者を理解し、大切に思う心がある人
- 臨床福祉学を学ぶための基礎学力*を有し、高い学修意欲および探求心のある人
- 福祉専門職として保健・医療・福祉の現場で活躍したいという強い意志を持つ人
- 福祉専門職として最新の知識・技術を常に学び続けようとする人
*基礎学力について
英語、数学、国語を高等学校等で履修しており、生体の成り立ちや活動を理解するうえで必要となる化学、生物、物理、大学のリベラルアーツ教育の基本となる世界史、日本史、地理、現代社会、政治・経済について、少なくとも1科目以上を履修していることをさします。
心理科学部臨床心理学科
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
心理科学部臨床心理学科の教育目標に基づき、卒業のために以下の要件を満たすことが求められる。
- 心の問題にかかわる職業人として必要な幅広い教養と専門的知識を修得している。
- 社会の変化、科学技術の進展に合わせて、教養と専門性を維持向上させる能力を修得している。
- 社会の様々な分野において、心の問題を評価し、それを適切に判断し援助できる基礎的技能を修得している。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
心理科学部臨床心理学科の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- 1年次には、大学教育へのスムーズな移行を図るために、導入科目を配当する。また、健康・運動科学および情報化社会への対応科目も1年次に配当する。
- 豊かな人間性・自立性・創造性・協調性等を身につけるために、教養科目を1年次から2年次に配当する。また、社会のグローバル化・多文化化に対応する外国語科目を1年次から2年次に配当する。
- 1年次から3年次にかけては、身体科学と対応した心の基礎的な知識を身につけるために関連する医療基盤科目、医療系科目を配当する。
- 1年次より、専門教育科目の体系化・構造化を図り、臨床心理専門領域の理解・深化を目的とした科目を配当する。また、1年次から4年次にわたって、公認心理師受験資格取得科目を配当し、国家資格に必要な知識・技能の修得を図る。
- 2年次より、多様な職業分野へのキャリア形成を図るため、進路支援科目・産業心理科目を配当する。また、心理臨床の基礎的技能を修得するために、1年次から4年次にわたって、コミュニケーション科目・心理療法科目を配当する。
- 3年次以降は、専門演習、心理文献講読等の科目履修を通して、自らのテーマによって教養と専門性を維持向上させる研究を実践する。
- 学修成果を把握・評価するために、筆記試験、ルーブリックを用いたレポート、実技試験などを実施する。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
心理科学部臨床心理学科では、学位授与の方針の要件を修得し、社会の要請と期待に応えて地域や人々の健康の向上に貢献できる心理専門職の養成を目標としています。そのため、以下のような資質を持った人材を広く求めます。
- 生命を尊重し、他者を理解し、大切に思う心がある人
- 心の問題に関心を持ち、他者を援助することに意欲を持っている人
- 入学後の修学に必要な基礎学力*を有している人
- 生涯にわたって学び、それを継続する意思を有している人
- 心理学の専門家として地域社会ならびに人類の幸福に貢献するという強い目的意識を持っている人
*基礎学力について
高等学校等で英語、国語等の履修により修得した基礎的知識に加えて、それらを活用し、自ら発展させていく意欲等を含むものをさします。
リハビリテーション科学部理学療法学科
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
リハビリテーション科学部理学療法学科の教育目標に基づき、卒業のために以下の要件を満たすことが求められる。
- 生命の尊厳と人権の尊重を基本とした幅広い教養、豊かな人間性、高い倫理観と優れたコミュニケーション能力を身につけている。
- 最新のリハビリテーション科学を理解し、保健・医療・福祉をはじめとするさまざまな分野において科学的根拠を有する専門技術を提供できる能力を身につけている。
- 理学療法士として必要な科学的知識や技術を備え、心身に障害を有する人、障害の発生が予測される人、さらにはそれらの人々が営む生活に対して、地域包括ケアの視点から適切に対処できる実践的能力を身につけている。
- 関係職種と連携し、質の高いチーム医療の実践的能力を身につけている。
- 国際的および地域的視野を有するリハビリテーションの専門家として活躍できる能力を身につけている。
- 社会の変化や科学技術の進歩に対応できるよう、常に専門領域の検証と、積極的な自己研鑽および理学療法科学の開発を実践できる能力を身につけている。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
リハビリテーション科学部理学療法学科の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- リハビリテーション専門職としてふさわしい豊かな人間性の形成、コミュニケーション力の向上を目的に、全学教育科目を1年次から3年次にわたって配当する。
- 1年次から2年次にかけては、科学的根拠に基づいた理学療法技術を実践するうえで理論的基盤となる専門基礎科目を中心に配当する。
- 3年次以降は、多様な障害に対して適切な理学療法を実践するために必要な治療ならびに支援技術を学ぶ科目を配当する。また、健康維持・増進の見地から、生活習慣病予防や介護予防、スポーツ障害予防等に対応できる科目も配当する。
- 3年次から4年次にかけては、研究法や研究セミナーの科目を配当し、社会の変化や科学技術の進展に合わせて、生涯にわたり自己研鑽していく態度を修得させる。
- 保健・医療・福祉の分野において、関係職種と連携するための協調的実践能力を養うために、多職種連携、地域連携に関する実践的な科目を配当する。
- リハビリテーション専門職である理学療法士としての態度、資質、行動を育成するとともに、学内教育で修得した知識と技術を統合させ、臨床実践能力を涵養するために、学外での臨床実習を各学年で段階的に展開する。
- 各授業科目の学修成果は、シラバスに明示された学修目標に対する教員よりの評価および学生アンケートなどの結果から達成状況を評価する。また、1年次における教養や基礎、2年次における臨床への指向、3年次における各専門領域の学修、4年次での総合的実践的能力の獲得といった各段階に応じた学修成果に加え、リハビリテーション科学部理学療法学科所定の教育課程における卒業要件への達成状況を単位取得状況やGPAにより評価する。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
リハビリテーション科学部理学療法学科では、学位授与の方針の要件を修得し、社会の要請と期待に応えて地域や人々の健康の向上に貢献できる理学療法専門職の養成を目標としています。そのため、以下のような資質を持った人材を広く求めます。
- 入学後の修学に必要な基礎学力*を有している人
- 協調性や基礎的な思考力と表現力を有している人
- 生命を尊重し、他者を大切に思う心がある人
- 保健・医療・福祉に関心があり、理学療法士として地域社会ならびに人類の幸福に貢献するという強い目的意識を持っている人
- 生涯にわたって学習を継続し、探求心を持ち、自己を磨く意欲を持っている人
*基礎学力について
高等学校等で修得する英語、数学、国語を基盤とし、生体の構造や機能を理解するための生物、化学、物理、および大学におけるリベラルアーツ教育の基盤となる社会系科目について1科目以上修得し身につけている学力をさします。
リハビリテーション科学部作業療法学科
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
リハビリテーション科学部作業療法学科の教育目標に基づき、卒業のために以下の要件を満たすことが求められる。
- 生命の尊厳と人権の尊重を基本とした幅広い教養、豊かな人間性、高い倫理観と優れたコミュニケーション能力を身につけている。
- 最新のリハビリテーション科学を理解し、保健・医療・福祉をはじめとするさまざまな分野において科学的根拠を有する専門技術を提供できる能力を身につけている。
- 作業療法士として必要な科学的知識や技術を備え、心身に障害を有する人、障害の発生が予測される人、さらにはそれらの人々が営む生活に対して、地域包括ケアの視点から適切に対処できる実践的能力を身につけている。
- 関係職種と連携し、質の高いチーム医療の実践的能力を身につけている。
- 国際的および地域的視野を有するリハビリテーションの専門家として活躍できる能力を身につけている。
- 社会の変化や科学技術の進歩に対応できるよう、常に専門領域の検証と、積極的な自己研鑽および作業療法科学の開発を実践できる能力を身につけている。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
リハビリテーション科学部作業療法学科の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- リハビリテーション専門職としてふさわしい豊かな人間性の形成、コミュニケーション力の向上を目的に、全学教育科目を1年次から3年次にわたって配当する。
- 1年次から2年次にかけては、科学的根拠に基づいた作業療法技術を実践するうえで理論的基盤となる専門基礎科目を中心に配当する。
- 3年次以降は、多様な障害に対して適切な作業療法を実践するために必要な治療ならびに支援技術を学ぶ科目を配当する。また、健康維持・増進の見地から、生活習慣病予防や介護予防、職業復帰の見地から就業支援等に対応できる科目も配当する。
- 3年次から4年次にかけては、研究法や研究セミナーの科目を配当し、社会の変化や科学技術の進展に合わせて、生涯にわたり自己研鑽していく態度を修得させる。
- 保健・医療・福祉の分野において、関係職種と連携するための協調的実践能力を養うために、多職種連携、地域連携に関する実践的な科目を配当する。
- リハビリテーション専門職である作業療法士としての態度、資質、行動を育成するとともに、学内教育で修得した知識と技術を統合させ、臨床実践能力を涵養するために、学外での臨床実習を各学年で段階的に展開する。
- 各授業科目の学修成果は、シラバスに明示された学修目標に対する教員よりの評価および学生アンケートなどの結果から達成状況を評価する。また、1年次における教養や基礎、2年次における臨床への指向、3年次における各専門領域の学修、4年次での総合的実践的能力の獲得といった各段階に応じた学修成果に加え、リハビリテーション科学部作業療法学科所定の教育課程における卒業要件への達成状況を単位取得状況やGPAにより評価する。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
リハビリテーション科学部作業療法学科では、学位授与の方針の要件を修得し、社会の要請と期待に応えて地域や人々の健康の向上に貢献できる作業療法専門職の養成を目標としています。そのため、以下のような資質を持った人材を広く求めます。
- 入学後の修学に必要な基礎学力*を有している人
- 協調性や基礎的な思考力と表現力を有している人
- 生命を尊重し、他者を大切に思う心がある人
- 保健・医療・福祉に関心があり、作業療法士として地域社会ならびに人類の幸福に貢献するという強い目的意識を持っている人
- 生涯にわたって学習を継続し、探求心を持ち、自己を磨く意欲を持っている人
*基礎学力について
高等学校等で修得する英語、数学、国語を基盤とし、生体の構造や機能を理解するための生物、化学、物理、および大学におけるリベラルアーツ教育の基盤となる社会系科目について1科目以上修得し身につけている学力をさします。
リハビリテーション科学部言語聴覚療法学科
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
リハビリテーション科学部言語聴覚療法学科の教育目標に基づき、卒業のために以下の要件を満たすことが求められる。
- 生命の尊厳と人権の尊重を基本とした幅広い教養、豊かな人間性、高い倫理観と優れたコミュニケーション能力を身につけている。
- 最新のリハビリテーション科学を理解し、保健・医療・福祉をはじめとするさまざまな分野において科学的根拠を有する専門技術を提供できる能力を身につけている。
- 言語聴覚士として必要な科学的知識や技術を備え、心身に障害を有する人、障害の発生が予測される人、さらにはそれらの人々が営む生活に対して、地域包括ケアの視点から適切に対処できる実践的能力を身につけている。
- 関係職種と連携し、質の高いチーム医療の実践的能力を身につけている。
- 国際的および地域的視野を有するリハビリテーションの専門家として活躍できる能力を身につけている。
- 社会の変化や科学技術の進歩に対応できるよう、常に専門領域の検証と、積極的な自己研鑽および言語聴覚療法科学の開発を実践できる能力を身につけている。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
リハビリテーション科学部言語聴覚療法学科の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- リハビリテーション専門職としてふさわしい豊かな人間性の形成、コミュニケーション力の向上を目的に、全学教育科目を1年次から3年次にわたって配当する。
- 1年次から2年次にかけては、科学的根拠に基づいた言語聴覚療法技術を実践するうえで理論的基盤となる専門基礎科目を中心に配当する。
- 3年次以降は、多様な障害に対して適切な言語聴覚療法を実践するために必要な治療ならびに支援技術を学ぶ科目を配当する。また、健康維持・増進の見地から、生活習慣病予防や介護予防、職業復帰の見地から就業支援等に対応できる科目も配当する。
- 3年次から4年次にかけては、研究法や研究セミナーの科目を配当し、社会の変化や科学技術の進展に合わせて、生涯にわたり自己研鑽していく態度を修得させる。
- 保健・医療・福祉の分野において、関係職種と連携するための協調的実践能力を養うために、多職種連携、地域連携に関する実践的な科目を配当する。
- リハビリテーション専門職である言語聴覚士としての態度、資質、行動を育成するとともに、学内教育で修得した知識と技術を統合させ、臨床実践能力を涵養するために、学外での臨床実習を各学年で段階的に展開する。
- 各授業科目の学修成果は、シラバスに明示された学修目標に対する教員よりの評価および学生アンケートなどの結果から達成状況を評価する。また、1年次における教養や基礎、2年次における臨床への指向、3年次における各専門領域の学修、4年次での総合的実践的能力の獲得といった各段階に応じた学修成果に加え、リハビリテーション科学部言語聴覚療法学科所定の教育課程における卒業要件への達成状況を単位取得状況やGPAにより評価する。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
リハビリテーション科学部言語聴覚療法学科では、学位授与の方針の要件を修得し、社会の要請と期待に応えて地域や人々の健康の向上に貢献できる言語聴覚療法専門職の養成を目標としています。そのため、以下のような資質を持った人材を広く求めます。
- 入学後の修学に必要な基礎学力*を有している人
- 協調性や基礎的な思考力と表現力を有している人
- 生命を尊重し、他者を大切に思う心がある人
- 保健・医療・福祉に関心があり、言語聴覚士として地域社会ならびに人類の幸福に貢献するという強い目的意識を持っている人
- 生涯にわたって学習を継続し、探求心を持ち、自己を磨く意欲を持っている人
*基礎学力について
高等学校等で修得する英語、数学、国語を基盤とし、生体の構造や機能を理解するための生物、化学、物理、および大学におけるリベラルアーツ教育の基盤となる社会系科目について1科目以上修得し身につけている学力をさします。
医療技術学部臨床検査学科
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
医療技術学部臨床検査学科の教育目標に基づき、卒業のために以下の要件を満たすことが求められる。
- 生命の尊重を基盤とした豊かな人間性、幅広い教養、高い倫理観を身につけている。
- 臨床検査に必要な知識と技術を修得し、先進・高度化する医療に対応できる実践能力を身につけている。
- 保健・医療・福祉の各分野の役割を理解し、チーム医療の一員としての自覚とそれを実践するための専門性と協調性を身につけている。
- 臨床検査のスペシャリストとして、進歩や変化に常に関心を持ち、生涯にわたり自己研鑽する姿勢を身につけている。
- 多様な文化や価値観を尊重し、地域的・国際的な視野で活躍できる能力を身につけている。
- 臨床検査学領域における様々な問題や研究課題に対し、解決に向けた情報の適切な分析、科学的思考と的確な判断ができる能力を身につけている。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
医療技術学部臨床検査学科の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- 1年次には、医療人としての豊かな人間性と幅広い教養を養う全学教育科目、さらに、チーム医療に求められるコミュニケーション能力を養い、多職種連携に関する理解を深めることを目的とした全学部学生が合同でおこなう科目を配当する。また、人体の構造や機能を学ぶ基礎医学科目や早期に臨床検査分野に対する動機付けを図るための臨床検査学の基礎に関する専門科目を配当する。
- 2年次には、臨床検査に対する理解を深め、専門知識を豊富にすることを目的とした臨床検査学の講義および実習科目を配当する。
- 3年次には、臨床検査技師に必要な技術を修得することを目的とした臨床検査学および関連する実習科目、さらに医療現場での臨床検査に関する知識を深め、臨床検査技師としての自覚を培うことを目的とした臨床実習を配当する。また、臨床の現場で実際に臨床検査技師が関わるチーム医療や在宅医療の理解、患者への接遇、リスクマネジメントの重要性を学ぶことを目的とした科目を配当する。
- 4年次には、研究を通して、科学的な思考による問題解決能力やプレゼンテーション能力を養うことを目的とした卒業研究を配当する。さらに、創造性、思考力、生涯にわたり自己研鑽する意欲を備え、指導的役割や教育・研究を担う臨床検査技師としての能力、同時に、先進・高度化する医療に対応できる能力を養うことを目的とした科目を配当する。
- 国際的な視野で活躍できる力の育成に向けて、1年次~4年次にわたって英語の科目、そして1年次に初修外国語(ドイツ語、中国語、ロシア語)を配当し、さらに、英米哲学の問題理解(人間と思想)、グローバルな観点からの自然環境・社会経済の変化と感染症(医療社会史)、欧米の医療保険制度(医療の経済学)などの異文化理解に関する科目を配当する。
- 学修成果を把握・評価するために、筆記試験、実技試験、ルーブリックを用いたレポート評価などを適宜実施する。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
医療技術学部臨床検査学科は、学位授与の方針の要件を修得し、医療社会の要請と期待に応えて地域や人々の健康の向上に貢献できる臨床検査専門職の養成を目標としています。そのため、以下のような資質を持った人材を広く求めます。
- 入学後の修学に必要な基礎学力*を有している人
- 協調性や基礎的な思考力と表現力を有している人
- 生命を尊重し、他者を大切に思う心がある人
- 保健・医療・福祉に関心があり、地域社会ならびに人類の幸福に貢献するという目的意識を持っている人
- 生涯にわたって学習を継続し、自己を磨く意欲を持っている人
*基礎学力について
医療技術学部臨床検査学科では、入学後、専門科目の基礎として、生体成分の化学的特性やその測定のための化学反応を理解するための化学、検査結果の妥当性を評価するための数学・統計学、生体情報の取得のための音や電気の特性を理解するための物理学、病気による生体成分や生体情報の変化を理解するための生理学・生化学・病理学などの科目があります。すなわち、高校で学習した数学、理科(化学、生物、物理)の知識や考え方を有効に活用することが学修成果を高めることにつながります。
ここに示す「基礎学力を有し」とは、上記科目を高校で履修していることをさします。
ただし、理科3科目全ての履修は限定されるため、少なくとも1科目を履修しており、未履修の科目については合格後に本学が提供する教育プログラムを受講することを推奨します。