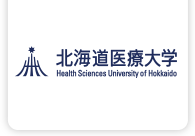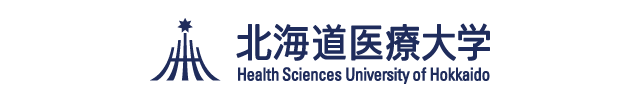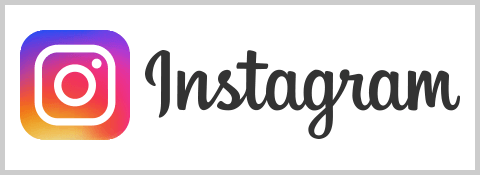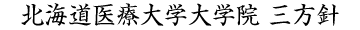- HOME
- 大学概要
- 北海道医療大学 三方針
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
北海道医療大学大学院では、教育理念・教育目的および教育目標に基づき、各研究科専攻において学位授与要件が定められています。各研究科専攻の定められた学位授与要件を満たし、高度な専門性と研究能力を修得したと認められる者に対して、「修士または博士」の学位を授与します。なお、本学大学院には以下の研究科および専攻を置きます。
薬学研究科:生命薬科学専攻(修士課程)
薬学専攻(博士課程)
歯学研究科:歯学専攻(博士課程)
看護福祉学研究科:看護学専攻(修士課程および博士課程)
臨床福祉学専攻(修士課程および博士課程)
心理科学研究科:臨床心理学専攻(修士課程および博士課程)
リハビリテーション科学研究科:リハビリテーション科学専攻(修士課程および博士課程)
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
北海道医療大学大学院研究科の各専攻(課程)では、教育理念・教育目的および教育目標に沿った学位授与の方針に基づく教育課程編成・実施の方針を定めており、「コースワーク」と「リサーチワーク」を適切に組み合わせた教育・研究課程を提供します。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
北海道医療大学大学院では、高度な専門知識・技術の修得と豊かな人間性を有する高度専門職業人の養成と最先端の研究活動を行える研究者・教育者としての人材を養成する研究・教育活動を行います。そのため研究科の各専攻(課程)ではこれらの目的に沿った学位授与の方針を定めており、学位授与の方針の要件をより効果的に達成しうる資質を持った人材について「入学者受入れの方針」として定めています。
なお、北海道医療大学大学院の教育理念・教育目的・教育目標に沿って、各研究科専攻(課程)の教育理念・教育目的・教育目標が定められています。
| 薬学研究科 | 歯学研究科 | 看護福祉学研究科 | 心理科学研究科| リハビリテーション科学研究科 |
薬学研究科生命薬科学専攻(修士課程)
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
以下の要件を満たし、生命薬科学における高度専門性と研究能力を修得したと認められる者に対して、「修士(生命薬科学)」の学位を授与する。
- 薬学研究科生命薬科学専攻(修士課程)に2年以上在学し、本研究科が定める履修上の要件を満たしている。
- 研究指導を受け、学位論文を提出し、本研究科が行う論文審査および最終試験に合格している。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
薬学研究科生命薬科学専攻(修士課程)の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- 志望研究分野に属して研究指導を受け、課題研究を通して問題発見能力および解決能力を身につけさせる。
- 幅広い視野から生命薬科学を学ぶことができるように配されたカリキュラムを通して、分野横断的に授業科目を履修させる。これにより高度専門職能の基礎となる豊かな学識を身につけさせる。
- 特論・演習科目の評価はプレゼンテーション・討論の参加状況やレポート等を用いて実施する。修士論文作成に当たり、指導担当教員による形成的評価を継続的に行い、研究態度、課題研究到達度および最終年次における研究発表会、修士論文審査基準に基づいて総合的に評価を行う。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
薬学研究科生命薬科学専攻(修士課程)では、学部において学んだ知識・技能をベースにして更に研鑽を積み、創薬科学あるいは医療科学それぞれの領域における、より高度な専門知識や理論・技術を修得して、地域の保健医療や福祉の増進、向上に携わることに強い意欲を持つ学生を求めます。
薬学研究科薬学専攻(博士課程)
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
以下の要件を満たし、深い学識と高い研究能力を修得したと認められる、あるいは高度な薬学専門性を必要とする職業において指導的役割を担うための高い学識と能力を修得したと認められる者に対して、「博士(薬学)」の学位を授与する。
- 薬学研究科薬学専攻(博士課程)に原則4年以上在学し、本研究科が定める履修上の要件を満たしている。
- 研究指導を受け、学位論文を提出し、本研究科が行う論文審査および最終試験に合格している。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
薬学研究科薬学専攻(博士課程)の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- 志望研究分野に属して医療薬学に関連する先端的研究に取り組みながら、研究計画能力と研究実践能力を身につけさせる。
- 学会発表ならびに論文発表を通して研究競争力と問題処理能力を身につけさせる。
- 幅広い視野から基盤薬学ならびに応用薬学を学ぶことができるように配された授業科目の履修を通して、所属研究分野の知識のみに偏ることなく分野横断的に医療薬学に拘わる高度専門知識を修得させる。これにより専門職能を発展する基礎となる豊かな学識を身につけさせる。
- 特論・演習科目の評価はプレゼンテーション・討論の参加状況やレポート等を用いて実施する。博士論文作成に当たり、指導担当教員による形成的評価を継続的に行い、3年次の「中間報告会」、最終年次における研究発表会、口頭試問、学力検査および博士論文審査基準に基づいて総合的に評価を行う。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
薬学研究科薬学専攻(博士課程)では、日進月歩の近代医療の中で、人々や他の医療従事者の多様なニーズに応えるために薬剤師として更なる高度専門知識を修得することを目指す学生、さらに医療薬学に関連する学問領域での最先端の研究に従事して自己研鑽を積み、地域医療の中核を担おうとする意欲を持つ学生を求めます。
歯学研究科歯学専攻(博士課程)
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
以下の要件を満たし、歯科医学の分野で、保健・医療・福祉の連携統合を担う研究者あるいは専門医として深い学識と高い研究能力を修得したと認められる者に対して「博士(歯学)」の学位を授与する。
- 歯学研究科歯学専攻(博士課程)に原則4年以上在学し、本研究科が定める履修上の要件を満たしている。
- 大学院3年次に、研究中間発表会で発表している。
- 研究指導を受け、学位論文を提出し、本研究科が行う論文審査および最終試験に合格している。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
歯学研究科歯学専攻(博士課程)では、「研究コース」と「認定医・専門医養成コース」の2つのコースを設けて、学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- 「研究コース」では、歯科医学研究を背景とした基盤的・先端的な専門知識および技能を修得させ、それらを統合する能力を備えた指導的な人材ならびに国際的に活躍できる自立した研究者を養成する。また、自己の研究に強い責任感と高い倫理性を持ち、その研究成果と意義を高度な水準で議論し、必要に応じて他の研究分野との協力体制を構築できる能力を育てる。そのための教育課程編成にあたっては、過度の専門化に陥ることなく、幅広い視野から自己の研究に係わる知識を集積できるよう学際的なカリキュラムを編成・導入し、既存概念に囚われることなく未踏の分野に挑戦する創造的な研究を実践させる。
- 「認定医・専門医養成コース」では、人々の多様かつ高度に専門的な医療サービスに対するニーズに応え、日々高度化する歯科医療技術を科学的エビデンスに基づいて評価し、それらを地域医療に応用できる研究マインドを持った臨床歯科医を養成する。 そのための本コースでは高度な歯科医療技術を修得させるばかりでなく、様々な歯科医療技術を多様な観点から評価し、それらの新規あるいは継続的導入が地域歯科医療の発展に貢献するか否かを絶えず客観的に検証できる能力を養成する。
- 歯科医学研究総論では、毎回の講義で実施する小テストあるいはレポート課題によって理解度を評価する。それ以外の特論・実習科目の評価は、プレゼンテーション・討論の参加状況やレポート等を用いて総合的に評価する。課題研究については、大学院2年目に研究構想検討会を実施して研究計画を公表し、指導担当教員以外に2名のアドバイザーを選出する。これらの教員が参加する研究成果計画検討会、3年目に実施する中間発表会、および最終年次における研究発表会を実施し、継続的に形成的評価を行い、研究態度、到達度を評価する。さらに提出された博士論文を主査・副査と学位論文提出者による討議会、および博士論文審査基準に基づいて総合的に評価する。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
歯学研究科歯学専攻(博士課程)では、基礎学力に加え、医療人としての高い倫理性を備え、自ら設定した目標達成のため粘り強く努力する意欲に富み、歯科医学の分野で保健・医療・福祉の連携統合を担う研究者あるいは専門医として人類の幸福に貢献するという強い意欲のある人材を求めます。
看護福祉学研究科看護学専攻(修士課程)
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
以下の要件を満たし、看護学における高度な専門性と研究能力を修得したと認められる者に対して、「修士(看護学)」の学位を授与する。
- 看護福祉学研究科看護学専攻(修士課程)に2年以上在学し、本研究科が定める履修上の要件を満たしている。
- 研究指導を受け、学位論文を提出し、本研究科が行う論文審査および最終試験に合格している。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
看護福祉学研究科看護学専攻(修士課程)の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- 教育・研究コース、高度実践コースの目的に対応し、専門領域の基礎となるコア科目として、実践力ならびに研究力を養成するため、特論・演習・実習および課題研究を系統的に配当する。
- 高度専門職業人の養成にむけ、判断力、役割遂行力を培う選択科目を配当する。
- 看護学と臨床福祉学に共通する研究法、およびコミュニティにおける看護と福祉の統合に関する科目を共通科目として配当する。
- 上記各コースの科目(特論・演習・実習)については、レポート・プレゼンテーション・討論の参加状況やルーブリック等を用いて評価する。修士論文の作成においては、指導担当教員による形成的評価を継続的に行い、1年次の「中間報告会」、最終年次における論文発表会および修士論文審査基準に基づいて総合的に評価を行う。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
看護福祉学研究科看護学専攻(修士課程)では、地域社会の発展ならびに人々の健康の向上に貢献できる高度専門職業人の養成を目標としています。そのため、以下のような資質を持った人材を広く求めます。
- 看護学における高度な専門知識および学術を修得し、自律的・創造的に活動する強い意欲がある人
- 社会の要請に対応する研究を推進し、地域社会や人々の健康向上に向けて深い探求心のある人
看護福祉学研究科看護学専攻(博士課程)
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
以下の要件を満たし、深い学識と高度な実践力、指導的役割の発揮力を修得したと認められる者に対して、「博士(看護学)」の学位を授与する。
- 看護福祉学研究科看護学専攻(博士課程)に3年以上在学し、本研究科が定める履修上の要件を満たしている。
- 研究指導を受け、学位論文を提出し、本研究科が行う論文審査および最終試験に合格している。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
看護福祉学研究科看護学専攻(博士課程)の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- 専門領域における実践力ならびに研究力を養成するために、特論・演習・特別研究を系統的に配当する。
- 高度実践または指導的役割遂行に必要な知識・技術を養成するため、選択科目を配当する。
- 看護学と臨床福祉学に共通した理論や開拓的研究を追究する科目として共通科目を配当する。
- 特論・演習科目については、プレゼンテーション・討論の参加状況やレポート等を用いて評価する。博士論文作成においては、指導担当教員による形成的評価を継続的に行い、最終年次における「中間研究報告会」、論文発表会、口頭試問、学力検査および博士論文審査基準に基づいて総合的に評価を行う。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
看護福祉学研究科看護学専攻(博士課程)では、高度な学識および独創的な研究力を有し、保健・医療・福祉分野において高度な実践を提供し指導的役割を担うことができる人材の養成を目標としています。そのため、以下のような資質を持った人材を広く求めます。
- 看護学における高度な専門知識および学術を修得し、実践あるいは教育分野において自律的・創造的に活動する意欲がある人
- 自立した研究者として、看護学の固有性や開拓的研究に向けて深い探求心のある人
看護福祉学研究科臨床福祉学専攻(修士課程)
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
以下の要件を満たし、臨床福祉学における高度な専門性と研究能力を修得したと認められる者に対して、「修士(臨床福祉学)」の学位を授与する。
- 看護福祉学研究科臨床福祉学専攻(修士課程)に2年以上在学し、本研究科が定める履修上の要件を満たしている。
- 研究指導を受け、学位論文を提出し、本研究科が行う論文審査および最終試験に合格している。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
看護福祉学研究科臨床福祉学専攻(修士課程)の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- 専門領域の実践力ならびに研究力を養成するため、コア科目として、特論・演習・実習および課題研究を系統的に配当する。
- 高度専門職業人の養成にむけ、判断力、役割遂行力を培う選択科目を配当する。
- 看護学と臨床福祉学に共通する研究法、およびコミュニティにおける看護と福祉の統合に関する科目を共通科目として配当する。
- 上記各コースの科目(特論・演習・実習)については、レポート・プレゼンテーション・討論の参加状況やルーブリック等を用いて評価する。修士論文作成においては、指導担当教員による形成的評価を継続的に行い、1年次の「中間報告会」、最終年次における論文発表会および修士論文審査基準に基づいて総合的に評価を行う。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
看護福祉学研究科臨床福祉学専攻(修士課程)では、地域社会の発展ならびに人々の福祉の向上に貢献できる高度専門職業人の養成を目標としています。そのため、以下のような資質を持った人材を広く求めます。
- 福祉学における高度な専門知識および学術を修得し、自律的・創造的に活動する強い意欲がある人
- 社会の要請に対応する研究を推進し、地域社会や人々の健康向上に向けて深い探求心のある人
看護福祉学研究科臨床福祉学専攻(博士課程)
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
以下の要件を満たし、深い学識と高度な実践力、指導的役割の発揮力を修得したと認められる者に対して、「博士(臨床福祉学)」の学位を授与する。
- 看護福祉学研究科臨床福祉学専攻(博士課程)に3年以上在学し、本研究科が定める履修上の要件を満たしている。
- 研究指導を受け、学位論文を提出し、本研究科が行う論文審査および最終試験に合格している。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
看護福祉学研究科臨床福祉学専攻(博士課程)の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- 専門領域における実践力ならびに研究力を養成するために、特論・演習・特別研究を系統的に配当する。
- 高度実践または指導的役割遂行に必要な知識・技術を養成するため、選択科目を配当する。
- 看護学と臨床福祉学に共通した理論や開拓的研究を追究する科目として共通科目を配当する。
- 特論・演習科目については、プレゼンテーション・討論の参加状況やレポート等を用いて評価する。博士論文作成においては、指導担当教員による形成的評価を継続的に行い、最終年次における「中間研究報告会」、論文発表会、口頭試問、学力検査および博士論文審査基準に基づいて総合的に評価を行う。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
看護福祉学研究科臨床福祉学専攻(博士課程)では、地域社会の発展ならびに人々の健康水準の向上に貢献できる高度専門職業人の養成を目標としています。そのため、以下のような資質を持った人材を広く求めます。
- 臨床福祉学における高度な専門知識および学術を修得し、実践あるいは教育分野において自律的・創造的に活動する意欲がある人
- 自立した研究者として、臨床福祉学の固有性や開拓的研究に向けて深い探求心のある人
心理科学研究科臨床心理学専攻(修士課程)
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
以下の要件を満たし、臨床現場において人の尊厳を重んじた科学者・実践家として自立できる者と認められ、修了後は公認心理師として社会に貢献することが期待できる能力を修得した者に対して、「修士(臨床心理学)」の学位を授与する。
- 心理科学研究科臨床心理学専攻(修士課程)課程に2年以上在学し、本研究科が定める履修上の要件を満たしている。
- 研究指導を受け、学位論文を提出し、本研究科が行う論文審査および最終試験に合格している。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
心理科学研究科臨床心理学専攻(修士課程)の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- 実証に基づく臨床心理学教育課程として、科学者・実践家モデルの視点を涵養しつつ、公認心理師を養成するカリキュラムを設ける。臨床現場に提供する人材の質を保証するために、関連する身体医学的領域の専門家ともチーム作業ができる実践家としての能力を育成するカリキュラムを設ける。
- 講義科目の評価はプレゼンテーション・討論の参加状況や筆記試験、レポート等を用いて評価する。実習の評価は、プレゼンテーション・討論の参加状況とクライアントのアセスメント結果および心理的支援の実技等を通して行う。修士論文作成に当たり、指導担当教員による形成的評価を継続的に行い、研究態度、課題研究到達度および最終年次における研究発表会、修士論文審査基準に基づいて総合的に評価を行う。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
心理科学研究科臨床心理学専攻(修士課程)では、保健・医療・福祉・教育、司法・産業の領域における心理臨床の高度専門家である公認心理師として、人類の幸福に貢献する志のある以下の資質を持った人材を求めます。
- 大学における公認心理師養成カリキュラムを履修し、入学後に必要な知識および技能を修得している人
- 心理臨床において、科学者実践家として幅広く心の問題に向き合う基礎的研究能力と志を有している人
心理科学研究科臨床心理学専攻(博士課程)
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
以下の要件を満たし、臨床現場、教育・研究領域において必要な指導的能力と研究能力を修得し、人の尊厳を重んじて、社会に貢献できると認められる者に対して、「博士(臨床心理学)」の学位を授与する。
- 心理科学研究科臨床心理学専攻(博士課程)に3年以上在学し、本研究科が定める履修上の要件を満たしている。
- 研究指導を受け、学位論文を提出し、本研究科が行う論文審査および最終試験に合格している。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
心理科学研究科臨床心理学専攻(博士課程)の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- 修士課程のカリキュラム履修を前提として、現場における指導者的能力、研究者としての能力を形成するために、基礎心理学および臨床心理学の両者にわたった幅広い教育カリキュラムを設ける。
- 講義科目の評価はプレゼンテーション・討論の参加状況やレポート等を用いて評価する。博士論文作成に当たり、指導担当教員による形成的評価を継続的に行い、最終年次における研究発表会、口頭試問、学力検査および博士論文審査基準に基づいて総合的に評価を行う。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
心理科学研究科臨床心理学専攻(博士課程)では、保健・医療・福祉・教育、司法・産業の領域における心理臨床の高度な教育指導者および研究者として、人類の幸福に貢献する志のある人材を求めます。
また、修士課程の能力に加えて、臨床の現場、教育・研究機関等において指導者となる志を持つ人材を求めます。
リハビリテーション科学研究科
リハビリテーション科学専攻(修士課程)
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
以下の要件を満たし、高度専門職業人としてリハビリテーション科学の実践に寄与できる優れた知識・技術と研究能力の基礎を修得したと認められる者に対して、「修士(リハビリテーション科学)」の学位を授与する。
- リハビリテーション科学研究科リハビリテーション科学専攻(修士課程)に2年以上在学し、本研究科が定める履修上の要件を満たしている。
- 研究指導を受け、学位論文を提出し、本研究科が行う論文審査および最終試験に合格している。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
リハビリテーション科学研究科リハビリテーション科学専攻(修士課程)の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- 授業科目は、リハビリテーション領域における高度専門職業人としての管理・指導能力や研究遂行能力の基盤を培う「共通科目」、最新の専門知識と技術を学び臨床実践能力を高める「専門科目」、関連学問領域を学ぶ「応用特色科目」、ならびに「研究指導」によって構成される。
- 共通科目には、組織をマネジメントする能力を育成するための教育法や管理学に加え、臨床研究を遂行する上で必要な研究法や統計学に関する科目を配当する。
- 専門科目には、各障害に対するリハビリテーション学分野の最新知識と技術、障がい者や高齢者などの地域生活支援に関して学ぶ科目を配当する。
- 応用特色科目には、学際領域であるリハビリテーション科学の臨床および研究実践に対応する上で必要な医科学系、心理学系、社会福祉学系の科目を配当する。
- 研究指導では、修士論文作成を行い、リハビリテーション科学における諸課題を追及する。
- 入学時志願者調査書や初期研究課題および学修カリキュラムにおける必修科目、選択科目の履修状況(修得単位数、GPA)、また、特論、演習科目の評価は、プレゼンテーション・討論の参加状況やレポート等を用いて評価する。修士論文作成に当たり、指導担当教員による研究指導を研究科として系統的に行い、課題研究達成度および最終年次における論文審査、最終試験、公開最終発表会により査定する。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
リハビリテーション科学研究科リハビリテーション科学専攻(修士課程)では、地域における保健・医療・福祉の充実に携わることに強い意欲を持ち、高度専門職業人としてリハビリテーションの実践に寄与すべく自己研鑽できる人材を求めます。
リハビリテーション科学研究科
リハビリテーション科学専攻(博士課程)
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
以下の要件を満たし、保健・医療・福祉の分野において、リハビリテーション科学に関する高度な学識と研究能力および教育能力を修得し、リハビリテーション科学の発展を通して社会に貢献できると認められる者に対して、「博士(リハビリテーション科学)」の学位を授与する。
- リハビリテーション科学研究科リハビリテーション科学専攻(博士課程)に3年以上在学し、本研究科が定める履修上の要件を満たしている。
- 研究指導を受け、学位論文を提出し、本研究科が行う論文審査および最終試験に合格している。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
リハビリテーション科学研究科リハビリテーション科学専攻(博士課程)の学位授与の方針に基づき、以下の方針のもとで教育課程を編成・実施する。
- 本専攻では、「生体構造機能・病態解析学分野」「リハビリテーション治療学分野」「地域健康生活支援学分野」の研究分野を設ける。
- 授業科目は、各分野における特講・演習、ならびに研究指導によって構成される。
- 研究指導では博士論文作成を行い、リハビリテーション科学を進化させ、科学的根拠を探求する。
- 学修目標に対する教員評価、修了生アンケートなどの結果に加え、単位取得状況やGPAにより査定する。特論、演習科目の評価は、プレゼンテーション・討論の参加状況やレポート等を用いて評価する。課題研究達成度および最終年次における論文審査、最終試験、公開最終発表会により査定する。また、研究能力を生かす高度医療専門職としての就業や就職率および研究への貢献を査定する。
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
リハビリテーション科学研究科リハビリテーション科学専攻(博士課程)では、リハビリテーション科学の発展に寄与し、リハビリテーション医療における科学的根拠を探究すべく先進的研究活動を実践できる研究者または指導的立場で活躍できる教育者および実践指導者を目指す強い意欲を持つ人材を求めます。