カタクリ
「カタクリ」はユリ科の多年草のことで、「エゾエンゴサク」、「ニリンソウ」とならび、雪どけ後の早春の明るい林床に大群落をつくる代表的な野草の一つです。花の色はとても美しい紫色で、それゆえ乱獲され、本州方面ではその個体数は激減しています。北海道ではまだ各地に大群落地が残っていて、札幌近郊でもゴールデンウイーク頃にかわいい花を見ることができます。「カタクリ」とう名の由来は「片栗」でクリの子葉の一片に似ていることからと言われていますが、他にも「カタクリ」には「堅香子(カタカゴ)」という古名があり、花の様子が「傾いた籠」に似ているから、それに「ユリ」がついて「カタコクリ」、さらにそれがつまって「カタクリ」と呼ばれるようになったという説もあり色々な説があるようです。
カタクリの鱗茎はかなり深い所にあり、10センチや20センチ掘っても鱗茎にたどりつかないこともあります。また、葉の表面には淡い紋があって株ごとに紋様が異なります。花のつく株には2枚の葉(時に3枚の時もある)があり、1枚の葉しかない株には花が咲きません。花の色もよく見ていると株によって濃淡があり、見ていてあきないものです。
「北海道」の名付け親として知られる、松浦武四郎は安政年間に蝦夷地を探検し、アイヌの人々と生活を共にしながら蝦夷地に関する膨大な試料を残した江戸時代の探検家です。彼の著書の一つに当時のアイヌの人々の食用植物として「延胡索、黒百合、山慈姑、車百合、菱実」の5つが絵つきで記されており、「山慈姑」には(フレエプイhure-epuy
= 赤い・花、かたくり)のルビがあり、これが「カタクリ」のことです。「カタクリ」の地下茎には40〜50%の澱粉粉が含まれており、「カタクリ粉」の名があるように、良質な澱粉が採取できますので古くから貴重な澱粉源として利用されていたであろうことは容易に想像できます。
さて、まえおきがかなり長くなってしみましたが、「カタクリ」の食べ方です。「カタクリ」の若葉を熱湯にくぐらせる程度に茹でた後、おひたし、マヨネーズあえ、ゴマあえ、カラシあえ、酢みそあえにして食べるのが一般的です。鱗茎は、すりおろして水にさらし、かたくり粉をとったり、甘煮、みそ煮などにして食べます。
北海道医療大学の所有する薬草園裏山にも一部「カタクリ」の群落があります。毎年5月上旬に渡辺山山頂に至る途中の西側斜面に「カタクリ」が咲き乱れます。同時期に咲く「エゾエンゴサク」の青紫色と「カタクリ」赤紫色のとの共演はとてもすばらしく早春の渡辺山の見どころの一つです。5月の連休あたり、ぜひご覧になって下さい。ただ、個体数がそれほど多いとはいえないので、見るだけにしておいて下さい。
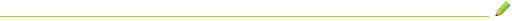
|



