後援会長メッセージ

北海道医療大学
後援会 会長
三上 章
我が大学が創立50周年を迎える事になりました。とても感慨深い思いです。
この半世紀を生き抜き、保健・医療・福祉業界に確固たる実績を残している事に畏敬の念を抱きます。音別の教養校舎。私は、“こんな不便な場所に大学を作るのは狂気の沙汰で、入学する学生はいないだろう”と言われていた一期生で、その不便な環境の中で沢山の思い出を作りました。教職員と学生との距離感が近く、この結び付きが最大の強みだったと思います。初代理事長が本学の同窓会活動が単なる親睦団体に留まることなく、同窓生全員が参加して専門の知識、技術の向上に役立つようなインテリジェンス・センターの役割を果たすものに向上する事を期待していると仰っておりましたが如何な評価でしょうか?
本後援会は、学生のご父母の皆様と卒業生一同、2万7千名を超える会員をもつ大きな支援組織です。学生の皆さんが充実した学生生活を送ることができるよう、また、皆様と学園との関係がより密接なものとなるよう、数々の活動を展開しています。
特に、10月から11月初旬までの土日祝日を利用して開催いたします「地区別懇談会」は毎年、ご父母の皆様と大学・専門学校教員との個別面談を実施しており、最も力を入れて取り組んでいる事業でございます。私事ですが、他学部の同窓生と会える機会でもあり、かけがえのない思い出になっております。
また、「国家試験対策助成」「就職活動助成」「医療機関受診時の自己負担費用を補助する診療費補助」等、学生生活へのサポートはもちろん、全国各地に後援会10支部を組織していますため、全国の卒業生に対しましても、情報提供や同窓会との連携によるセミナーの開催等により、絶えず情報発信をしているところでございます。
後援会といたしましては、学園創立50周年を迎え、我々の後輩となる入学生の皆さんが充実した学生生活を送れるよう、できる限りの努力をして参りたいと存じます。
関係各所の皆様におかれましては、温かいご支援とご理解を賜りますようお願い申し上げます。
同窓会長メッセージ

薬学部
同窓会長
桂 正俊
北海道医療大学創立50周年おめでとうございます。
今まで大学を支えていただきました教職員の皆様と事務局員をはじめとした東日本学園の関係者の皆様そして父母後援会の皆様に厚く感謝申し上げます。
6,500名を超える薬学部同窓会会員を代表して一言お祝い申し上げます。
薬学部からスタートした東日本学園大学は、1期生が入学してから50年の時が流れているという事で1期生が特に思い出深いと思います。私は12期生で音別キャンパスが最後であるとともに、当別キャンパスの教養部で最初に学んだ学生でもあり、大学の大きな歴史の1ページを過ごしたと思っております。 娯楽もないのに語らい合った音別の寮生活、吹雪で立ち往生した当別の冬、薬品の匂いが懐かしい専門教室等どれも仲間と過ごしたかけがえのない大学生活でした。また、大学時代に学んだ恩師の教えは、社会人となった今でも大切な教科書となっております。薬学教育が6年制となり、OSCE(客観的臨床能力試験)の評価者として大学に出入りする卒業生が多くなり、教員とのコミュニケーションがとれ、後輩の育成ができる機会ができたことはさらに愛校心が深まっているのではないでしょうか。
現在、北海道医療大学は6学部9学科1専門学校の医療系総合大学までに成長し、最近では地域の多職種連携やチーム医療でも北海道医療大学卒の医療・福祉・介護の関係者が多くなり非常にコミュニケーションが取りやすくなりました。今後は薬学部同窓会のみの活動だけではなく他の学部の同窓会とコラボし連携を取ることで医療系総合大学の特権を活かして行けたらと考えております。
最後に北海道医療大学の益々の発展をお祈り申し上げるとともに、薬学部同窓会として大学運営に少しでもお役に立てるよう努力してまいります。

歯学部
同窓会長
蓑輪 隆宏
1978(昭和53)年4月、私は東日本学園大学歯学部第1期生、149名のうちの1人として入学させて頂きました。
私が今、歯科医師として、またこのような立場で寄稿させて頂きますこと大変光栄に存じます。
振り返りますと、先輩のいない1期生は、何を頼りに国家試験まで進めば良いのか分からず、毎日が恐れと不安の学生生活でしたが、厳しくも愛溢れる教職員の皆様そして強い絆で結ばれた素晴らしい仲間のおかげで、何とか目標を達成出来たのは、この学舎があったからこそと感じております。
あの道東、霧の原野、音別町での寮生活、そして猛吹雪で死にかけた暴風雪の地、当別町での勉強と実習。これは他大学の歯学部では考えられないものだった思いますが、今となってはどれもこれも貴重な修行でした。
なかでも、忘れられないのは国家試験前の寒い年末年始、大学のバスで向かった旭川の山奥、天人峡温泉での勉強合宿です。学生の会1期会が企画したこれは全員参加の合宿で数人ずつ部屋に入れられ朝から夜遅くまでどんどん配られるテストと解説を黙々とこなさなければならず、それはとてもハードなものでした。風邪やストレスで体調を崩す仲間が続出し、結局、期間途中で打ち切られ挫折して札幌に戻ることになりました。
そんな辛く苦しい経験もあってか、卒業を決めた1期生は、心も身体も強くなり、当然のごとく全員、国家試験に合格し、大学関係各位の皆さんの期待に応えることが出来た時は皆、鼻高々でした。
この春歯学部は41期生が卒業し、同窓会は本年2024年秋、晴れて設立40周年を迎えます。それぞれの学部で卒業生の皆様が紡いでこられた歴史がありますが、大学の黎明期を過ごした歯学部1期生の一人として、この経験をお伝えし母校がこれからの100年そして200年とさらにキラキラ輝くことを心から祈念し母校創立50周年の寄稿とさせて頂きます。

看護学科
同窓会長
川村 武昭
北海道医療大学が創立50周年を迎えられますことを心よりお祝い申し上げます。
この記念すべき年に同窓会である福慧会の会長としてお祝いできますことを大変光栄に感じております。
さて、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を契機にICTの活用が進み、テレワークやwebによる会議や研修など公私ともに生活様式が大きく変わりました。そしてこのデジタル化への流れは、その利便性等を鑑みれば、今後益々進むことと感じるところです。私が勤める保健所においても様々なシステムが導入されたことで、工夫次第で出来ることの幅が広がったことに大きな可能性を感じておりますが、その一方で、これらを活用するための能力も求められていると感じているところです。それは電子機器やシステムなどを扱うための知識や技術もそうなのですが、webなどにより対面することが出来ない相手との関係性を構築するためのコミュニケーションやプレゼンテーション能力、そして相手の状況を推し量り共感する能力が求められているように感じています。現在、様々な分野において人口減少等の影響による担い手不足を背景に関係職種間の連携なくして質の高いミッションの達成が困難な状況下、デジタル化の波がその障害にならないよう、むしろ促進のきっかけとなるような考え方の変革が必要だと感じています。私が今後大学に期待したいことは、現代社会において人とコミュニケーションを取ることの意義や必要性、そして対面で話が出来ることの意味を考え、行動できる医療人の育成です。これまでは人と「話す」ことと「会う」こととはある意味同義、当たり前のことでしたが、現在は、一度も直に会うことのない相手と関係性や信頼関係を構築し、困難なプロジェクトやミッションに取り組むことが日常となりました。6学部9学科を擁する医療系総合大学の本学ならではの素敵な方法で強靭な多職種連携をマネジメントできる専門職業人を育てていって欲しいと期待しています。
この50年という浅からぬ歴史の荒波を乗り越え、幾多の人材を輩出してきた北海道医療大学が今後益々発展していくことをこころから願っております。

福祉マネジメント学科
同窓会長
小畑 友希
私の医療大との出会いは、阪神淡路大震災があった1995年に遡ります。当時神戸の医療機関で働きながら進学を目指していた時に震災に遭い、同僚が医療大の編入学試験の新聞広告を見つけたところから始まります。大阪の試験会場の面接官は、現在私が所属するさっぽろひかり福祉会の理事長です。現在の職場のつながったのも、学生時代に佐々木敏明先生に紹介してもらったことがきっかけです。卒論では、精神障がいのある人たちの自己決定について考察するために、精神科病院で入院中の患者さんのお話を聞きたいとゼミの先生に相談したらところ、任意実習もさせていただきました。それらのことが卒業後の進路に繋がり現在にまで及んでいます。振り返ると、遠慮がないなと恥ずかしくなりますが、在学生の皆さんには、ぜひ先生方に甘えて学生特権として図々しく学んで欲しいなと思います。
現在、精神や発達に障がいのある人たちの労働や相談に関する事業の運営を担っていますが、福祉をマネジメントすることは、地域社会を豊かにすることにつながることだと思います。障がいのある人たちが地域で働くことを通して、社会が多様性を理解し受け止めることになり、さらには地域に必要とされ、経済活動にも一役担うことにもなります。福祉という糸口から社会を変革することも不可能ではない分野です。創立100周年の頃には、医療大で培った創造力と連帯の精神で、障害のある人もない人も分け隔てないことが当たり前となっている文化が根付いていることを願いたいと思います。

臨床心理学科
同窓会長
上河邊 力
北海道医療大学が創立50周年を迎えられましたこと、心よりお慶び申し上げます。臨床心理学科同窓会を代表して、ご挨拶を申し上げます。
私が北海道医療大学の臨床心理学科へ入学したのは、2007年のことです。そこから大学院修了まで過ごした6年間は、私にとって本当に特別なものでした。私は、そこでの多くの出会いが、1人の人間として、そして1人の専門家としての今の私を形作っていると強く感じています。当時の心理科学部はあいの里キャンパスに全ての機能が集約されていました。あいの里キャンパスは当別キャンパスに比べると小さな校舎ですが、今思えば幸せな環境だったように思います。同級生はもちろん、先輩や後輩、先生がたとも毎日のように顔を合わせました。空き時間はロビーや食堂に集まるのが習慣で、大半の時間は、一緒にゲームに明け暮れたり先輩や後輩と進路や就職についてざっくばらんに語り合ったりする穏やかな光景が広がっていました。しかし、いざ試験前になると皆が真剣な顔になり、同じ目標を持った学友たちと互いに励まし合いながら勉強に取り組みました。その時築いた人間関係は今でも途切れずに残っており、ある人とは専門家同士として、ある人とは1人の友人として頼りになる存在になりました。また、先生方も1人1人の学生を気遣い、親身になってくださっていることをいつも実感していました。先生方は、いつでも学生の可能性に目を向けて期待をこめて声をかけてくださいました。今思えば、先生方は学生と接するその姿勢をもって、対人支援職となる人間のありようを教えてくださっていたように思います。
そんな、私にとって宝物のような場所である北海道医療大学が、今後も100年、200年と一層の繫栄と発展を遂げ、引き続き高度な専門性と豊かな人間性をもった人材を世に送り出していかれることを期待しています。

理学療法学科
同窓会長
白幡 吏矩
北海道医療大学が創立50周年を迎えることを、2万3千名を超える卒業生の1人として大変嬉しく、誇らしく感じます。
かくいう私は、現役の博士課程の学生でもありますが、学部生時代を回想すると、同期と過ごした日々や白熱した球技大会のドッジボール、長期にわたる臨床実習を思い出すなかで、何よりも忘れられない出来事は「卒業式の中止」です。2020年3月に卒業を迎えた私たち理学療法学科4期生は、感染症の流行により卒業式を迎えることができませんでした。
国家試験翌日、自己採点により学年全員が合格ラインを超えたことが分かり盛り上がるなか、吉田晋先生と宮崎充功先生が教壇上で固い握手を交わしていたあの瞬間が同期全員が集まった場での最後の思い出となっていることを懐かしく感じます。
最近では、北広島へのキャンパス移転に関する話題への学内外の方からの注目度の高さを感じています。唯一無二の環境でスタートを切る新キャンパスにおいて北海道医療大学の理学療法学科でしか経験することのできない特徴が新たに生まれていくことを期待するとともに、理学療法学科同窓会がその一助となるよう尽力する所存です。
昨年末に開催されました東日本学園・同窓会役員懇談会では関係者の皆様の「想い」を拝聴し、北海道医療大学は次の節目に向けて発展していくことを確信いたしました。少子化、感染症の流行による医療職離れなど医療系総合大学としては厳しい社会状況でございますが、50周年を一つの通過点とし、北海道医療大学が発展し続けるよう個人として、理学療法学科同窓会して邁進して参ります。

作業療法学科
同窓会長
田丸 仁啓
この度は大学関係者の皆様、在校生/卒業生の皆様、創立50周年誠におめでとうございます。私自身もこの歴史ある道内唯一の医療系総合大学である本学に携わることが出来ていることを大変嬉しく思います。
私は作業療法学科の一期生として入学し、当初は同学部の先輩がいないことへの不安をやや抱えながら大学生活をスタートさせたことを覚えています。しかし、学部/学科を問わず同級生の存在や教員の方々のサポート、部活動の先輩方の安心感によりすぐに払拭し瞬く間にコニュニティーが広がっていきました。大学の4年間といえば、バイトに時間を費やした人、友との時間を大切にした人、旅行に多く出かけた人、ボランティア活動をした人、お酒を覚えた人、それぞれ時間の使い方は様々ですが家庭を持った今、大学4年間は大変貴重な時間であったと実感します。
今もその当時に絆を深めあった仲間とは、切磋琢磨しあえる同業者として、時にはパパ/ママ友として非常に大切な存在です。
本学は50周年、作業療法学科は昨年で10周年を迎え、更なる医療系総合大学としての飛躍を期待したいと思います。少子化、診療報酬改定等々逆風が多々吹いているのは既知の事実ですが、北広島市への移転を最高の追い風として更なる発展をしていくことを祈願するかつ私自身も微力ながら今後も本学のために努力して参ります。
この度は誠におめでとうございました。
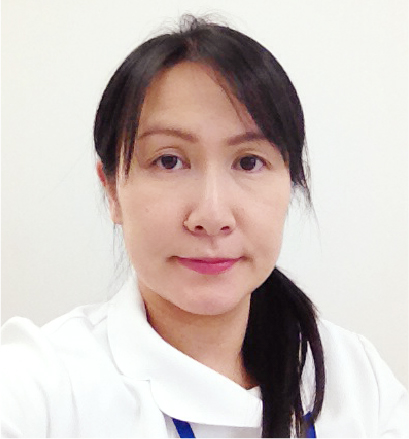
言語聴覚療法学科
同窓会長
石黒 恵美子
大学の関係者の皆様、創立50周年誠におめでとうございます。
本学リハビリテーション科学部言語聴覚療法学科の前身は札幌医療福祉専門学校の言語聴覚療法学科でした。設立時、言語聴覚士はまだ国家資格になっていませんでしたが、将来的なSTへのニーズの高まりを見越し、いち早く学ぶ環境を整えてくださった法人の皆様と先生方に、卒業生一同深く感謝しております。
私は1999年から2年間専門学校の2年課程専攻科に在学していました。当時のエピソードを少しお伝えします。2年時の臨床実習の際、見知らぬ土地での長期実習で挫けそうになっていた所へ、担当の先生が陣中見舞に来てくださいました。温かくアドバイスをいただき、心強く感じたことを覚えています。また、情報が少ない中、先生方が問題演習や模擬試験等の国家試験対策を懸命に行って下さいました。学生も先生方に応え、仲間同士支え合いながら必死で勉強し、2001年第3回目の国家試験に臨みました。同級生の合格率は高く、出来が良くない自分も何とか合格できたのは先生方のお陰です。本当にありがとうございました。
学科はのちに大学の心理科学部言語聴覚療法学科に移行、更にリハビリテーション科学部の中の1学科となりました。北海道でPT・OT・STの3学科が全て揃っている大学は本学のみです。他学科や他学部との共学、交流を通じて早くから「チーム医療」を学べる環境は本学の大きな特長です。
この度の北広島への移転計画を知った時は大変驚きましたが、計画の詳細をうかがい、不安はなくなりました。新しい土地のメリットを活かし、今後も一層時代に求められる優れた医療・福祉人の育成を通じて、地域社会に貢献してゆく本学の未来の姿を想像し、この先の50年にも大きな期待を抱いています。
今後も同窓会としてお役に立てることがあれば、大いに協力して参りたいと存じます。

医療技術学部
同窓会長
古高 裕導
北海道医療大学創立50周年という記念すべき節目の瞬間を、一同窓生として迎えられることを心から嬉しく感じております。
この時に至るまでに多くの大学関係者並びに先生方のご尽力があったことと思っております。そんな方々のおかげでこうして今、学生が安心して学業に励み、医療に携わる夢を追うことができるのだと思っております。
医療技術学部は昨年初の卒業生を出したばかりです。創立50年の歴史において本学部はまだまだ若い学部ではありますが、他学部と同様に正しい知識と知恵、技術をもった医療人を育成・輩出することで、これからの「北海道医療大学」に貢献していくことを期待しています。医療技術学部同窓会も卒後教育の一環として勉強会やセミナーを企画・開催し、また定期的に懇親会を設けるなど、同窓会活動を通して学部在学生・同窓生を様々な面からサポートしていきます。
50周年記念事業企画委員長であり本大学の副学長である和田啓爾先生は、本学にとって創立50周年は「通過点」の一つであり「ゴール」ではないのだと仰っておりました。そのお言葉通り、50周年という節目を超えてますます北海道医療大学が北海道医療大学らしく発展し続けていくことを期待しております。
これからも北海道医療大学が、学生また同窓生にとってより良い学びの場であり続けることを願っております。

歯学部附属
歯科衛生士専門学校
同窓会長
梶 美奈子
1980年代18歳の少女は、期待に胸膨らませて歯学部附属歯科衛生士専門学校の門をくぐりました。歯科衛生士がどのような仕事を成す職種なのか全くわからぬままに。。。
当時は、薬学部、歯学部と歯科衛生士専門学校のみを有する校舎でしたが、それでも大きくて近代的な建物に感じていました。
高校までは、ほとんど同一地域に生まれ育ち文化や風習に共通点を持つクラスメートと共に学びましたが、歯科衛生士学校には道内各地、道外からも学生が集まっており、年齢も様々でした。「さすがに歯学部附属だわ〜」と感じていました。
勉強や実習は、思ったより大変でした。似たような形に見えるのに名前の違う器具、なかなか検印がいただけない実習帳、再提出、再再提出はいつものこと。今思えば、実習担当歯科衛生士さんもよくあそこまで付き合ってくれたものだと思います。あの頃意地悪に思えた方にも感謝しなければなりません。
数々の苦難を乗り越えて到達した国家試験は、筆記試験と実技試験の2段階方式で、どちらも試験前にクラスメートや先生たちと必死に勉強しました。当時は、お付き合いいただいた先生たちに感謝する気持ちは全くありませんでしたが、今は一人の歯科衛生士として、同窓会長として、先輩として、人に学びを伝えることの難しさ、重大さ、責任の重さを身に染みて感じております。
現在50代半ばを過ぎたあの頃の少女は、長い歯科衛生士生活の中で一度も違う職種に就きたい、仕事をやめたいと思ったことはありません。諦めずに、根気強くご指導し続けてくださった皆様のおかげで今現在があるのだと思います。
<在学中の皆様、今後入学される皆様へ>
私は学生時代、根気強く指導していただいたのだと今になって感じています。皆様はどのようにお感じになるのか?TRYしてみてはいかがでしょうか?。
